全年全月23日の投稿[30件](2ページ目)
2024年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
2023年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
自宅の本棚を整理していたら「空飛ぶ円盤製作法」なる書籍を発掘。
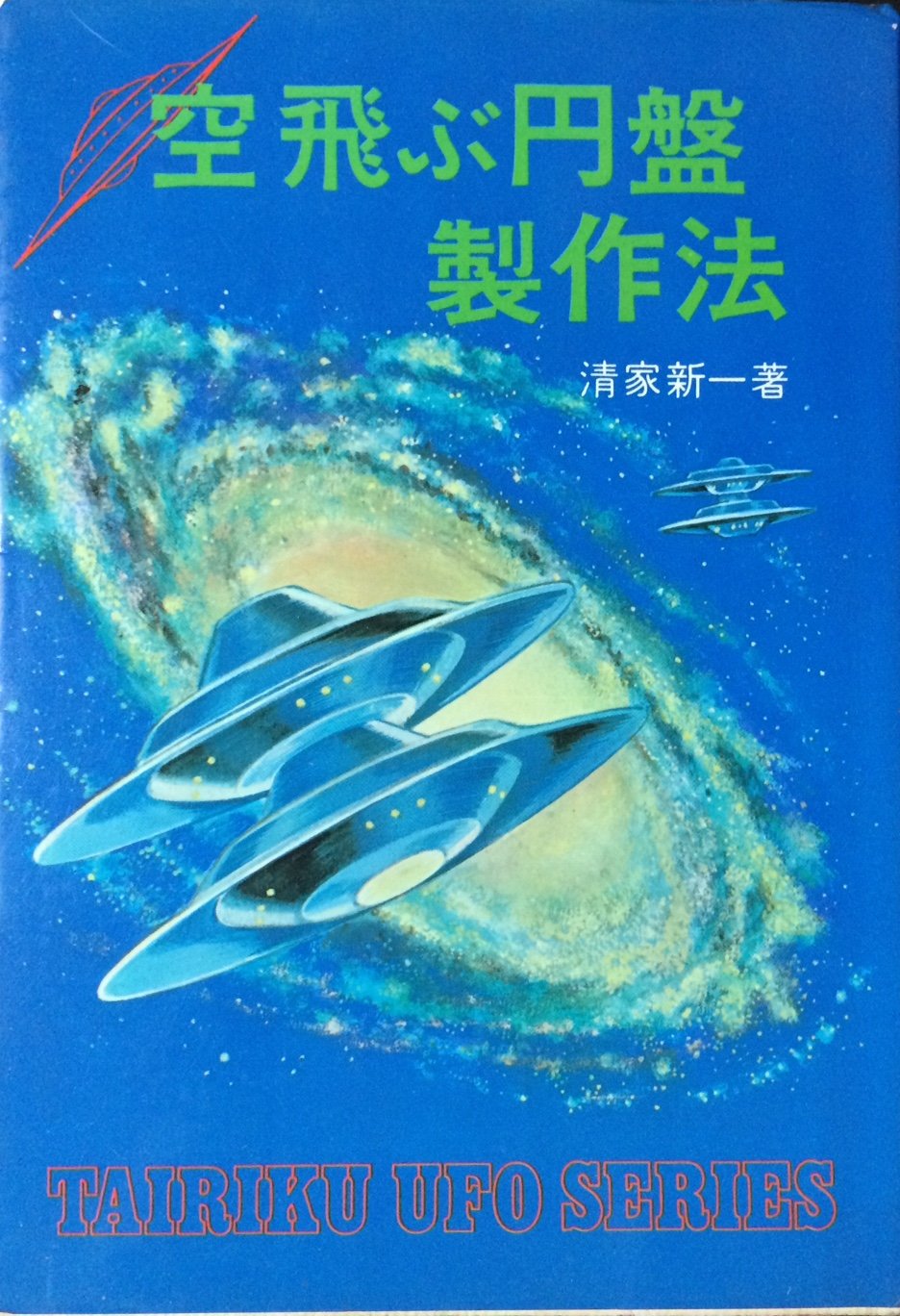
中学生だか高校生だか、厨二病真っ盛りの頃に買った思い出があるので懐かしー。
内容は難しい数式の羅列。たぶん、理系大学レベルの数学だと思われますので全く理解できません。
一つだけ面白いなぁ~って思ったのは、電場を高速回転させることで重力に反する(相当する)力場を作れるって話。
オカルト方面のネタになりますが、コマは回転中にほんの少しだけ軽くなるとの説もあり、物体は高速で回転すると軽くなるとかなんとか。
前出の書籍によりますと「電場を3GHzの三相交流で回転させる」とあります。物質を3GHzの周期で回転させるなど不可能だと思いますが、物質を回転させずに電場の状態を回転させるなら3GHzも不可能ではないでしょう。今どきのパソコンも3GHzで動くCPUはザラですからね。
回転中のコマが持つ電場が構成する物質に対して一定の位置関係ならコマの電場も回転していると見立てることが出来ます。高速回転が静止状態と違った物理現象を起こすならば、この本で言うところの電場を高速で回すことに興味が湧きます。
厨二病当時の自分が今の知識を持っていたらこんな妄想をしただろうなぁ~って話www
ただ、3GHzの三相交流を作ることには今の自分が興味深々です。これを作れたらインバーター回路の神になれそうです。
#雑談
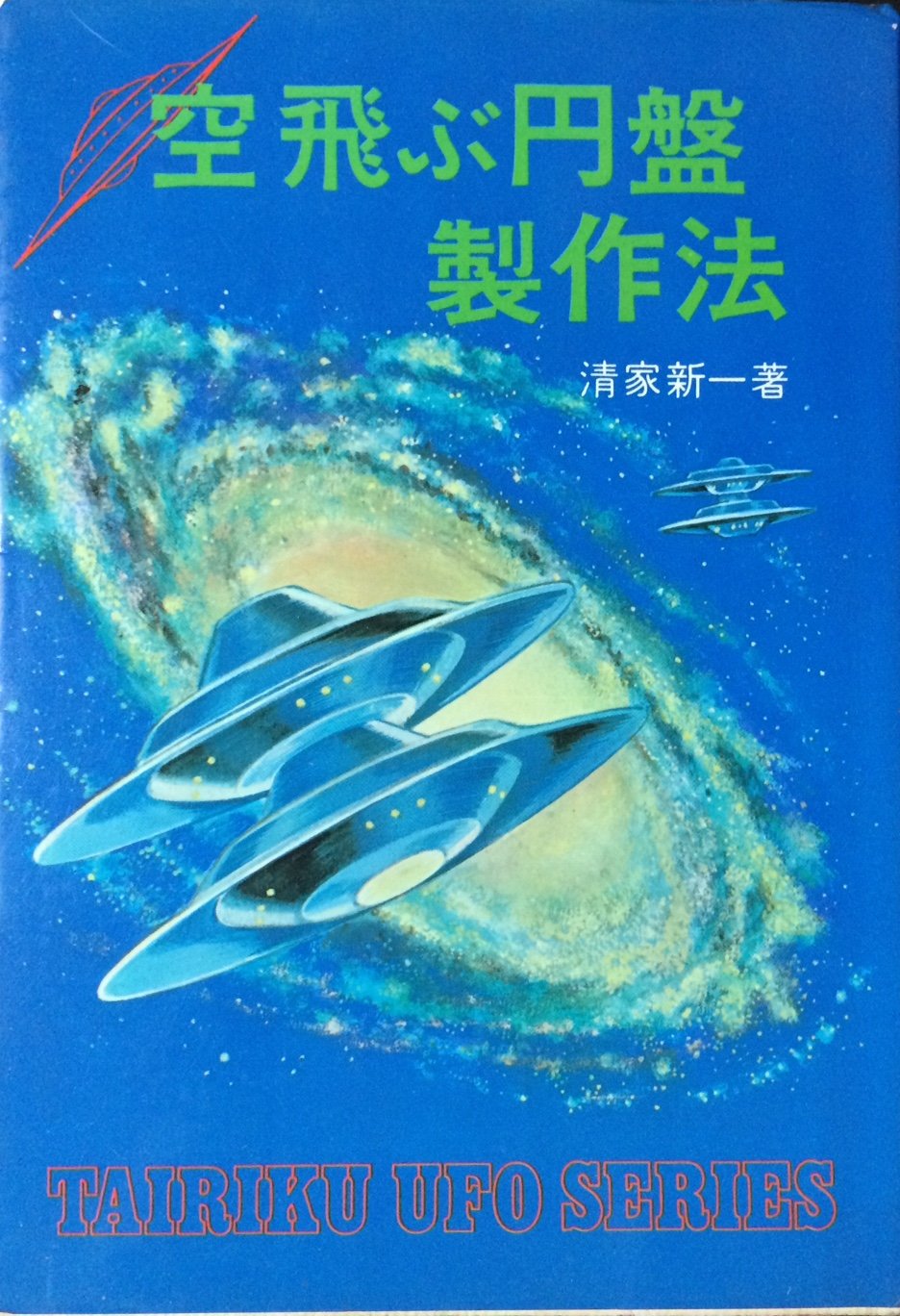
中学生だか高校生だか、厨二病真っ盛りの頃に買った思い出があるので懐かしー。
内容は難しい数式の羅列。たぶん、理系大学レベルの数学だと思われますので全く理解できません。
一つだけ面白いなぁ~って思ったのは、電場を高速回転させることで重力に反する(相当する)力場を作れるって話。
オカルト方面のネタになりますが、コマは回転中にほんの少しだけ軽くなるとの説もあり、物体は高速で回転すると軽くなるとかなんとか。
前出の書籍によりますと「電場を3GHzの三相交流で回転させる」とあります。物質を3GHzの周期で回転させるなど不可能だと思いますが、物質を回転させずに電場の状態を回転させるなら3GHzも不可能ではないでしょう。今どきのパソコンも3GHzで動くCPUはザラですからね。
回転中のコマが持つ電場が構成する物質に対して一定の位置関係ならコマの電場も回転していると見立てることが出来ます。高速回転が静止状態と違った物理現象を起こすならば、この本で言うところの電場を高速で回すことに興味が湧きます。
厨二病当時の自分が今の知識を持っていたらこんな妄想をしただろうなぁ~って話www
ただ、3GHzの三相交流を作ることには今の自分が興味深々です。これを作れたらインバーター回路の神になれそうです。
#雑談
2023年8月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
EoCの試験の続きでArt-Netを通してみました。全く問題なく動きます。繋いだだけで動いたので試行錯誤は無し。
接続は次の通りです。配線が汚いのはテストなのでご勘弁を。

[MAdot2]
↓ Cat5e
[Ethernetハブ]
↓ Cat5e
[PoEインジェクタ] ← <AC100v>
↓ Cat5e(PoEとして電源供給線も兼ねるので細いケーブルは非推奨)
[EoCレシーバ]
↓ A2V1B(3C相当) 50m
[EoCトランスミッタ]
↓ Cat5e
[Ethernetハブ]
↓ Cat5e
[Art-Net Node]
↓ XLR 5P
[DoctorMA]
↓ USB2.0
[パソコン]
エフェクトエンジンのデータで半日くらい様子を見てみます。
トランスミッタとレシーバは逆にしても動きます。
DMXのモニターにはDoctorMXを使っていますが、信号の遅れなのかDoccorMXの遅れなのか、ほんのわずかに遅れを感じるかもしれません。
しばらく先になりますが、現場で使えるパッケージも考えないといけません。これらを毎回組んでいたら面倒ですからね。
箱の中にそれぞれの用品を固定し、パネルに取り口を付けようと思います。これにUPSやインカムのパワーサプライも同居させたら便利かなと。
EoCのレシーバとトランスミッタはそこそこ熱を持つのでパッケージにおいては冷却を考慮した方がいいですね。こうったバラバラの物をパッケージする際はベース板を合板にした方が楽ですが、底板をアルミにした筐体放熱も検討の余地ありです。
#[Art-Net]
接続は次の通りです。配線が汚いのはテストなのでご勘弁を。

[MAdot2]
↓ Cat5e
[Ethernetハブ]
↓ Cat5e
[PoEインジェクタ] ← <AC100v>
↓ Cat5e(PoEとして電源供給線も兼ねるので細いケーブルは非推奨)
[EoCレシーバ]
↓ A2V1B(3C相当) 50m
[EoCトランスミッタ]
↓ Cat5e
[Ethernetハブ]
↓ Cat5e
[Art-Net Node]
↓ XLR 5P
[DoctorMA]
↓ USB2.0
[パソコン]
エフェクトエンジンのデータで半日くらい様子を見てみます。
トランスミッタとレシーバは逆にしても動きます。
DMXのモニターにはDoctorMXを使っていますが、信号の遅れなのかDoccorMXの遅れなのか、ほんのわずかに遅れを感じるかもしれません。
しばらく先になりますが、現場で使えるパッケージも考えないといけません。これらを毎回組んでいたら面倒ですからね。
箱の中にそれぞれの用品を固定し、パネルに取り口を付けようと思います。これにUPSやインカムのパワーサプライも同居させたら便利かなと。
EoCのレシーバとトランスミッタはそこそこ熱を持つのでパッケージにおいては冷却を考慮した方がいいですね。こうったバラバラの物をパッケージする際はベース板を合板にした方が楽ですが、底板をアルミにした筐体放熱も検討の余地ありです。
#[Art-Net]
EoCは割り切った仕様で好みです。
ただ、youtubeの視聴でテストをしていたのですが一度だけ通信が落ちていたことがあります。 原因はわかりませんが、十分に検証する必要はありそうです。
原因はEoC、LAN、インターネット、パソコン、youtubeなどの構成するすべてとその組み合わせにまで可能性あるだけに絞り込むのは困難でしょう。何かに問題があっても実用レベルで動けばいいのですけどね。そもそも、即応性は二の次として開発されたEthernetでライブ制御をするのですから潜在的な問題だと思いますが・・・。
現時点ではパソコンをインターネットに接続する試験でしたので、卓からのArt-Netでノードを動かす試験をします。パソコンがインターネットに繋がるなら動くと思いますケド。
現時点のコストですが、設備用の5C-FBが19,800円/100m、カナレさんのA2V1Bが59,800円/100m、カナレさんのDMX203が19,800円/100mです。
100mbpsでArt-Netを通せるなら実用域は8ユニバース以上です。何を基準に評価するかですが、仮に4ユニバースとして、DMX203を4本に対しArt-Net&EoCシステム、同軸ケーブルのコストを比較すると若干EoCに分があります。
コストに大差がなく配線長に優位性があるならEoCを研究する価値があるように思います。
#[Art-Net]
ただ、youtubeの視聴でテストをしていたのですが一度だけ通信が落ちていたことがあります。 原因はわかりませんが、十分に検証する必要はありそうです。
原因はEoC、LAN、インターネット、パソコン、youtubeなどの構成するすべてとその組み合わせにまで可能性あるだけに絞り込むのは困難でしょう。何かに問題があっても実用レベルで動けばいいのですけどね。そもそも、即応性は二の次として開発されたEthernetでライブ制御をするのですから潜在的な問題だと思いますが・・・。
現時点ではパソコンをインターネットに接続する試験でしたので、卓からのArt-Netでノードを動かす試験をします。パソコンがインターネットに繋がるなら動くと思いますケド。
現時点のコストですが、設備用の5C-FBが19,800円/100m、カナレさんのA2V1Bが59,800円/100m、カナレさんのDMX203が19,800円/100mです。
100mbpsでArt-Netを通せるなら実用域は8ユニバース以上です。何を基準に評価するかですが、仮に4ユニバースとして、DMX203を4本に対しArt-Net&EoCシステム、同軸ケーブルのコストを比較すると若干EoCに分があります。
コストに大差がなく配線長に優位性があるならEoCを研究する価値があるように思います。
#[Art-Net]
2023年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
エージングの仕方を少し変え、これまでは抑えめの信号でしたが、歪まないギリギリのところから3dBくらい下げたレベルのピンクノイズを与えることにしました。
海外の某メーカーのテクニカルノートにかなり高いレベルの信号を与えてエージングを行うとの記述があったためです。正解は不明ですが、メーカーが言うならやってみるべきです。
これが功を奏したのかわかりませんが、3時間後にチェックしたところダイナミックレンジが明らかに広がっていました。MUSES01Dはエージングが済むと出力レベルが高めになりダイナミックレンジが広がるとのレポートもありますので、ちょうどそういう変化が起こるタイミングだったのかもしれませんけどね。
これまでは無改造品に比べ少しだけ良い感じが続いていましたが、改造品が徐々に差を広げ始めています。
#音の世界
海外の某メーカーのテクニカルノートにかなり高いレベルの信号を与えてエージングを行うとの記述があったためです。正解は不明ですが、メーカーが言うならやってみるべきです。
これが功を奏したのかわかりませんが、3時間後にチェックしたところダイナミックレンジが明らかに広がっていました。MUSES01Dはエージングが済むと出力レベルが高めになりダイナミックレンジが広がるとのレポートもありますので、ちょうどそういう変化が起こるタイミングだったのかもしれませんけどね。
これまでは無改造品に比べ少しだけ良い感じが続いていましたが、改造品が徐々に差を広げ始めています。
#音の世界
MUSES01Dに換装したDI-1はエージングが110時間ほど経過し安定してきました。昨日の中域が詰まった安っぽい音は解消しています。
無改造品より良いのですが、手間暇お金をかける程の印象はまだありません。
良い点を特筆するなら、生ギターの高音弦やハイポジションは圧倒的に良いことです。弦が擦れる音や細い響きに立体感があります。
ダイレクトボックスの役目は楽器のレベル変換ですし、DI-1の不満点は高域の詰まった感じですから、これはこれで良いのかもしません。
ただ、並列で音を通している無改造品も日に日に良くなってきている印象があります。
上記の特筆点では改造品に負けますが、エージングしたら無改造品でもいいんじゃないか!?という予感もしています。
ちょっと違う分野ですが、次の様なyoutube動画がありました。
「エイジングするとエフェクターの音はどう変わるのか」
MUSES01D化したDI-1はもっと変わります。
#音の世界
無改造品より良いのですが、手間暇お金をかける程の印象はまだありません。
良い点を特筆するなら、生ギターの高音弦やハイポジションは圧倒的に良いことです。弦が擦れる音や細い響きに立体感があります。
ダイレクトボックスの役目は楽器のレベル変換ですし、DI-1の不満点は高域の詰まった感じですから、これはこれで良いのかもしません。
ただ、並列で音を通している無改造品も日に日に良くなってきている印象があります。
上記の特筆点では改造品に負けますが、エージングしたら無改造品でもいいんじゃないか!?という予感もしています。
ちょっと違う分野ですが、次の様なyoutube動画がありました。
「エイジングするとエフェクターの音はどう変わるのか」
MUSES01D化したDI-1はもっと変わります。
#音の世界
2023年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
3Dプリンタは期待値が出る様になりました。
樹脂成型は難しいですね。
期待値は出たものの、5.7mmにしたM3六角(5.5mm)を挿す穴が緩い。5.5mm丁度は危険なので期待値を5.6mmにして再度プリント中。
5.5mmに対する5.7mmは3.6%の違い。たかが0.2mm、されど0.2mm、一見小さな数字ですがこれだけのクリアランスでガバ付きを感じるんですね。たぶん、丸穴なら気にならないのでしょうけど。
#3Dプリンタ
樹脂成型は難しいですね。
期待値は出たものの、5.7mmにしたM3六角(5.5mm)を挿す穴が緩い。5.5mm丁度は危険なので期待値を5.6mmにして再度プリント中。
5.5mmに対する5.7mmは3.6%の違い。たかが0.2mm、されど0.2mm、一見小さな数字ですがこれだけのクリアランスでガバ付きを感じるんですね。たぶん、丸穴なら気にならないのでしょうけど。
#3Dプリンタ
2022年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
もう数日頑張れば本業が落ち着きます。夏休み前の小学生みたいにワクワクした気持ちですが何をしましょう。
手つかずの課題は特盛です。自由に何でも出来そうな解放感はあっても時間も気力も体力も資金も有限です。
物理装置を作るのもいいのですが、暖かい部屋に籠ってヌクヌクと出来る課題がいい。
まずはArt-Netエンジンですかね。これが出来れば幾つかの課題をクリアするキーになります。
調光制御の底辺で必要になる計算ライブラリも重要でしょうか。レベル値にマスタ値を与えて出力値を得るとか、幾つかのレベル値をマージするライブラリです。調光卓的なシステムでは必須です。
さらにはANSIエスケープシーケンスを用いた画面表示ライブラリです。これはpythonが苦手なfor文を多用せずには書けないのでC言語で書くのが必須だからです。
明日は数か月ぶりの完全オフなのでゆっくり考えましょう。
追記
ゆっくり考えようと思ったのですが、アホみたいに疲れが出て何も出来ませんでした。
アドレナリンに頼って誤魔化すと反動が酷いお年頃。
#雑談
手つかずの課題は特盛です。自由に何でも出来そうな解放感はあっても時間も気力も体力も資金も有限です。
物理装置を作るのもいいのですが、暖かい部屋に籠ってヌクヌクと出来る課題がいい。
まずはArt-Netエンジンですかね。これが出来れば幾つかの課題をクリアするキーになります。
調光制御の底辺で必要になる計算ライブラリも重要でしょうか。レベル値にマスタ値を与えて出力値を得るとか、幾つかのレベル値をマージするライブラリです。調光卓的なシステムでは必須です。
さらにはANSIエスケープシーケンスを用いた画面表示ライブラリです。これはpythonが苦手なfor文を多用せずには書けないのでC言語で書くのが必須だからです。
明日は数か月ぶりの完全オフなのでゆっくり考えましょう。
追記
ゆっくり考えようと思ったのですが、アホみたいに疲れが出て何も出来ませんでした。
アドレナリンに頼って誤魔化すと反動が酷いお年頃。
#雑談
今扱っている課題ではハードウェアの処理能力を出来るだけ主題の処理に振り向けたいのです。
C/C++の使用やポインタの活用は大いに貢献しそうですが、プロセス間通信をポインタを介して行うことは今時のOSでは無理っぽい。プロセスの独立性をOSがガッチリ固めるからです。
プロセス間で通信するにはOSがマネージするpipeや共有メモリを用いないといけません。幸い、pythonで同様のことをするよりも処理速度が速いようなので現実的ではありますが、このレベルの情報になりますとその筋の上級者が書いているので前提が高度で完全理解には程遠いところです。もっと基礎を固めないといけません。
現時点では同プロセス内でのスレッド処理で構成するのが現実的かなと。
同プロセス内ならポインタを介してスレッド間で変数を共有できるそうです。
ただ、Art-Netエンジン(受信/パッチ/送信の一連処理)を独立したプロセスにしたいので、いずれはプロセス間通信を多用出来る技術も習得しないといけません。
理解には及んでいませんが、芸は無いけど速度が出せる共有メモリが一番良さそうです。
追記
プロセス間でのメモリ共有
説明は少ないですが、サンプルコードに余計な装飾がありませんし、ほぼANSI-Cで書かれているので理解しやすい。
共有メモリを宣言し、そのメモリのアドレスを数値としてポインタ変数に渡しているだけです。別プロセスへのアドレスの渡し方が地味ですが、動作を理解するにはこれでいいのです。単に値が渡ればいいのか、特別な手段で渡すのか、明確にわかります。
これを習得出来たら楽になりますね。
#C言語
C/C++の使用やポインタの活用は大いに貢献しそうですが、プロセス間通信をポインタを介して行うことは今時のOSでは無理っぽい。プロセスの独立性をOSがガッチリ固めるからです。
プロセス間で通信するにはOSがマネージするpipeや共有メモリを用いないといけません。幸い、pythonで同様のことをするよりも処理速度が速いようなので現実的ではありますが、このレベルの情報になりますとその筋の上級者が書いているので前提が高度で完全理解には程遠いところです。もっと基礎を固めないといけません。
現時点では同プロセス内でのスレッド処理で構成するのが現実的かなと。
同プロセス内ならポインタを介してスレッド間で変数を共有できるそうです。
ただ、Art-Netエンジン(受信/パッチ/送信の一連処理)を独立したプロセスにしたいので、いずれはプロセス間通信を多用出来る技術も習得しないといけません。
理解には及んでいませんが、芸は無いけど速度が出せる共有メモリが一番良さそうです。
追記
プロセス間でのメモリ共有
説明は少ないですが、サンプルコードに余計な装飾がありませんし、ほぼANSI-Cで書かれているので理解しやすい。
共有メモリを宣言し、そのメモリのアドレスを数値としてポインタ変数に渡しているだけです。別プロセスへのアドレスの渡し方が地味ですが、動作を理解するにはこれでいいのです。単に値が渡ればいいのか、特別な手段で渡すのか、明確にわかります。
これを習得出来たら楽になりますね。
#C言語