全年全月31日の投稿[24件]
2025年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
アタマがヒマな時にArtNetPatch の処理構成を考えています。
今日は現地照明の卓番でしたから時間はありました。居なきゃいけない、トラブル無ければやることない、もちろん寝てもいけない。こんな置きダヌキは妄想にふけるに限ります。
今のところ、Art-Net に流れているデータを表示するモニターから作ってみようかと。必要になるテクニックのほとんどを使うことになるので習作になりますし処理負荷が見えます。卓を何枚相手に出来るか、何ユニバース相手に出来るかの検討材料になります。
RaspberryPi-CM4 を母体に使う予定ですが、高性能を求めるのではなく RaspberryPi で作れる範囲の最高スペックを形にすることが課題です。昨年の試作では RaspberryPi4で卓3枚、入力合計12ユニバース、出力4ユニバースくらいならいけそうでした。ミキサーとしても使えるプロファイルカーブ・ディレイ付きのパッチマシンが欲しいワケですが、自分の仕事ではこの規模で御の字です。RaspberryPi を使う理由は安くて小さくて電気喰わなくて PIC などのマイコンと協調しやすいからです。PCレベルのマザーボードにSPIやI2Cが付いていればそれでもいいのですけど、それが期待できる工業用のマザーボードは一般のPCマザーボードに比べてお高いのです。
RaspberryPi上のDebianベースで作っておけば、ほぼそのまま工業用マザーボードに持って行ける期待感があります。Windowsベースでは難しいことですが、Debian(Linux)ベースでの製作はメリットが多いのです。
#[Art-net]
今日は現地照明の卓番でしたから時間はありました。居なきゃいけない、トラブル無ければやることない、もちろん寝てもいけない。こんな置きダヌキは妄想にふけるに限ります。
今のところ、Art-Net に流れているデータを表示するモニターから作ってみようかと。必要になるテクニックのほとんどを使うことになるので習作になりますし処理負荷が見えます。卓を何枚相手に出来るか、何ユニバース相手に出来るかの検討材料になります。
RaspberryPi-CM4 を母体に使う予定ですが、高性能を求めるのではなく RaspberryPi で作れる範囲の最高スペックを形にすることが課題です。昨年の試作では RaspberryPi4で卓3枚、入力合計12ユニバース、出力4ユニバースくらいならいけそうでした。ミキサーとしても使えるプロファイルカーブ・ディレイ付きのパッチマシンが欲しいワケですが、自分の仕事ではこの規模で御の字です。RaspberryPi を使う理由は安くて小さくて電気喰わなくて PIC などのマイコンと協調しやすいからです。PCレベルのマザーボードにSPIやI2Cが付いていればそれでもいいのですけど、それが期待できる工業用のマザーボードは一般のPCマザーボードに比べてお高いのです。
RaspberryPi上のDebianベースで作っておけば、ほぼそのまま工業用マザーボードに持って行ける期待感があります。Windowsベースでは難しいことですが、Debian(Linux)ベースでの製作はメリットが多いのです。
#[Art-net]
2025年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
新年度、女子の部下が1名増えます。専門学校卒なので二十歳です。
すでに同世代の女子部下が3名いますので4姉妹の父親になった気分です。
本当の親ではありませんので結婚話やら私生活には立ち入りませんが、4姉妹を一人前にするにはどうしたものか悩めるお父さんなのでした。
仕事に緊張感と責任感を持たせるなら昭和的に厳しくするのもアリですが、Z世代とも呼ばれる子たちは要領はいいけど打たれ弱い傾向にあります。客や他社の先輩たちと直接やりとりが出来る気配りやメンタルを身に付けさせることが一番難しいなぁ~なんて思ったりして。
30代の野郎が2名いますが同じような心配はしてあげません。
#雑記
すでに同世代の女子部下が3名いますので4姉妹の父親になった気分です。
本当の親ではありませんので結婚話やら私生活には立ち入りませんが、4姉妹を一人前にするにはどうしたものか悩めるお父さんなのでした。
仕事に緊張感と責任感を持たせるなら昭和的に厳しくするのもアリですが、Z世代とも呼ばれる子たちは要領はいいけど打たれ弱い傾向にあります。客や他社の先輩たちと直接やりとりが出来る気配りやメンタルを身に付けさせることが一番難しいなぁ~なんて思ったりして。
30代の野郎が2名いますが同じような心配はしてあげません。
#雑記
2025年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
Antari F1-FAZER の排煙器の焦げカス除去に「ジクロロメタン」を使うのはどうだろう。3Dプリンタの製作物の表面処理で使ってますが、セルロース、エステル、油脂、樹脂を溶かす性質があるそうな。スモークリキッドの焦げカスも溶かしてくれないだろうか。発煙器は高温になるので内部に樹脂やゴムの部品は無いものと予想していますが、そうならジクロロメタンで侵されることは無いハズです。
気をつけなければならないのは毒物であることです。吸引すると呼吸器系に良くないそうな。
どのように施工するか考えてみましょう。
追記
ジクロロメタンで溶けないOリングやパッキンはフッ素樹脂(PTFE)だそうな。ステンレス製の調理用注射器を用い、パッキンをフッ素樹脂製に変えればよいのかな?
#器具の修理
気をつけなければならないのは毒物であることです。吸引すると呼吸器系に良くないそうな。
どのように施工するか考えてみましょう。
追記
ジクロロメタンで溶けないOリングやパッキンはフッ素樹脂(PTFE)だそうな。ステンレス製の調理用注射器を用い、パッキンをフッ素樹脂製に変えればよいのかな?
#器具の修理
2024年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
10年以上前に作った調光ユニットでフリッカーが出るとの話しがありました。状況を再現出来ないので原因がわかりませんでしたが、予防策を突然閃く。ACのゼロクロス時にはSCRへのトリガー信号を強制的に切るのです。ある意味簡単なことですが、なかなか思い付かなかった自分に反省。調光装置は望むレベルで点灯させるのが役目ですが、確実に消灯することがとても大事です。
フリッカー発生条件ので検証は不可能ですが、マイコンのファームウェアを修正したところ前よりもSCRのスイッチングが安定しているようです。
ソースコードのコメントを数年後の自分への申し送りとして事細かに書いていたことも助けになりました。勢いで書き殴って動いたらオシマイとしていたら解決出来なかったかもしれません。
#電子工作 #照明器具
フリッカー発生条件ので検証は不可能ですが、マイコンのファームウェアを修正したところ前よりもSCRのスイッチングが安定しているようです。
ソースコードのコメントを数年後の自分への申し送りとして事細かに書いていたことも助けになりました。勢いで書き殴って動いたらオシマイとしていたら解決出来なかったかもしれません。
#電子工作 #照明器具
2024年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
C言語ネタです。
セマフォを使ったプロセス間での排他制御
セマフォは異なるプロセスが共有メモリへ同時に読み書きをしないために使おうを思っています。この記事だけではどう使ったらいいか見えませんが、セマフォの機能についてはシンプルに要点を突いて分かりやすい。こういう蛇足が無い説明は好きです。
ここでは他のプロセスの挙動は説明されていませんが、同じ名前のセマフォ(この記事では"/unko")を開いて同じ様に使います。同じセマフォを持った二つのプロセスがあるとして、後から sem_wait(sem) を実行した側は先に sem_wait(sem) を実行した側が sem_post(sem) を実行するまでブロック(動作を一時停止)します。sem_trywait(sem) を用いればブロックせずに戻りますので戻り値を見て処理を続行出来ます。
自力でセマフォを作ろうと思っていましたが、この方法でいいんでないかなと。
セマフォの方針が決まれば必要なことが一通りまとまったことになるので書き始められそうです。
まずは Art-Net を丁寧に受信する処理から進めます。ネットワーク上のすべての ArtDMX(スロットデータが列挙されたパケット) と存在する送信機の一覧を取得し、別プロセスから読み出して階層的に表示することを当面の目標とします。一種の Art-Net モニタでしょうか。画面を横に3分割し、左に送信機の一覧、中間に選択された送信機が扱うユニバース、右にスロットデータといった構成です。送信機とユニバースをキーボード(カーソル)操作で選択することも習作の一部となります。
これが作れなければ ArtNetPatch など作れませんし、最終的なパッケージでも欲しい機能です。
#C言語
セマフォを使ったプロセス間での排他制御
セマフォは異なるプロセスが共有メモリへ同時に読み書きをしないために使おうを思っています。この記事だけではどう使ったらいいか見えませんが、セマフォの機能についてはシンプルに要点を突いて分かりやすい。こういう蛇足が無い説明は好きです。
ここでは他のプロセスの挙動は説明されていませんが、同じ名前のセマフォ(この記事では"/unko")を開いて同じ様に使います。同じセマフォを持った二つのプロセスがあるとして、後から sem_wait(sem) を実行した側は先に sem_wait(sem) を実行した側が sem_post(sem) を実行するまでブロック(動作を一時停止)します。sem_trywait(sem) を用いればブロックせずに戻りますので戻り値を見て処理を続行出来ます。
自力でセマフォを作ろうと思っていましたが、この方法でいいんでないかなと。
セマフォの方針が決まれば必要なことが一通りまとまったことになるので書き始められそうです。
まずは Art-Net を丁寧に受信する処理から進めます。ネットワーク上のすべての ArtDMX(スロットデータが列挙されたパケット) と存在する送信機の一覧を取得し、別プロセスから読み出して階層的に表示することを当面の目標とします。一種の Art-Net モニタでしょうか。画面を横に3分割し、左に送信機の一覧、中間に選択された送信機が扱うユニバース、右にスロットデータといった構成です。送信機とユニバースをキーボード(カーソル)操作で選択することも習作の一部となります。
これが作れなければ ArtNetPatch など作れませんし、最終的なパッケージでも欲しい機能です。
#C言語
音響も照明もデジタルコンソールを使うのが日常となりました。
これらはとても高機能で便利な機器ですが、弱点を申し上げるなら起動に時間がかかることと、瞬間停電で動作不良に陥ることがあることです。
機器に与える電源は半仮設なことが多いためコネクタの脱落や接点不良の可能性は拭えず、老朽化した劇場ですと空調器等の動作によっては瞬間停電に等しい状態に陥ることもあります。
完全停電ならともかく、瞬間停電による動作不良はクライアントに理解を得ることが難しく、ストレージへのアクセス中に電源が落ちますとシステムが深刻な支障に至ることもあります。
前置きが長くなりましたが、瞬間停電や数分の停電があってもコンソールの動作を維持する対策を施したいので「無停電電源装置」を使いたい。いわゆる「UPS」です。
UPSのバックアップ方式には様々な種類があるのでどんな状況でも安心とは言い切れませんが、無いよりは明らかに事故率を下げられます。
ただ、UPS製品は据え置きを前提にした物が多く、仕込んでバラしてを繰り返すと物理的に傷みやすい。
ならばと思ったのが、デスビとUPSをラックケースに1パッケージにしたモノはどうだ?というアイデア。デスビとはノイズフィルタとサージカットを提供する電源分配装置と言えばいいでしょうか。欲しいのは瞬間停電に対策し、電源ノイズを軽減し、サージカットをする物です。安価なUPSでもサージカットは入っています。ノイズフィルタまで入っている物は重装備の設備用となりますが、コモンモードフィルタを入れれば事足ります。
私の印象ですが、UPSと言えば「OMRON」さん。安価な普及品から高性能な重装備品まで幅広くラインナップし、何よりも保守用の交換バッテリーの入手に安心感があります。バッテリーの寿命は3-5年のため、安いだけ品はいざ交換したいときにバッテリーが手に入らないこともあるからです。
コンソール周りの消費電力は300wくらいが平均でしょうか。上には上がありますが、一番頻度の高い条件を一般条件とし、もっと必要なら複数使うなり専用品として対策する方向で。
OMRONさんの製品で19インチラックにマウント出来そうな安価な製品ですと「BX50F」でしょうか。
「BX50F」
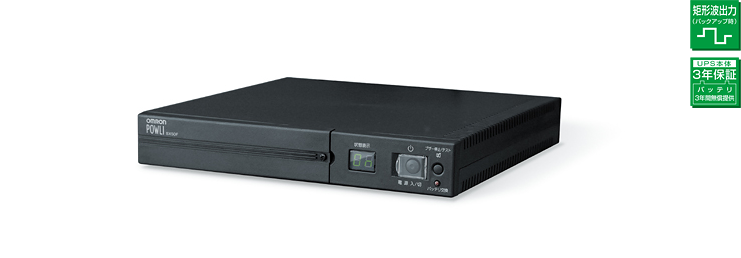
バックアップ容量は500VA/300wなのでもう一息欲しい気もしますが、小型軽量だし、空冷余白や付属パネルを含めても2Uに収まりそうなので実用的かなと。
実は、OMRONさんのBZ50LT2をすでに使っています。一見安っぽいのですが十分に使えています。事故に遭遇したことはありませんが、試験停電させたところ数分保持しました。卓周辺で単体の消費電力が300wを越える製品は多くありませんし、BX50Fは形が違うだけで同等の製品ですから十分使えるでしょう。
#照明器具
これらはとても高機能で便利な機器ですが、弱点を申し上げるなら起動に時間がかかることと、瞬間停電で動作不良に陥ることがあることです。
機器に与える電源は半仮設なことが多いためコネクタの脱落や接点不良の可能性は拭えず、老朽化した劇場ですと空調器等の動作によっては瞬間停電に等しい状態に陥ることもあります。
完全停電ならともかく、瞬間停電による動作不良はクライアントに理解を得ることが難しく、ストレージへのアクセス中に電源が落ちますとシステムが深刻な支障に至ることもあります。
前置きが長くなりましたが、瞬間停電や数分の停電があってもコンソールの動作を維持する対策を施したいので「無停電電源装置」を使いたい。いわゆる「UPS」です。
UPSのバックアップ方式には様々な種類があるのでどんな状況でも安心とは言い切れませんが、無いよりは明らかに事故率を下げられます。
ただ、UPS製品は据え置きを前提にした物が多く、仕込んでバラしてを繰り返すと物理的に傷みやすい。
ならばと思ったのが、デスビとUPSをラックケースに1パッケージにしたモノはどうだ?というアイデア。デスビとはノイズフィルタとサージカットを提供する電源分配装置と言えばいいでしょうか。欲しいのは瞬間停電に対策し、電源ノイズを軽減し、サージカットをする物です。安価なUPSでもサージカットは入っています。ノイズフィルタまで入っている物は重装備の設備用となりますが、コモンモードフィルタを入れれば事足ります。
私の印象ですが、UPSと言えば「OMRON」さん。安価な普及品から高性能な重装備品まで幅広くラインナップし、何よりも保守用の交換バッテリーの入手に安心感があります。バッテリーの寿命は3-5年のため、安いだけ品はいざ交換したいときにバッテリーが手に入らないこともあるからです。
コンソール周りの消費電力は300wくらいが平均でしょうか。上には上がありますが、一番頻度の高い条件を一般条件とし、もっと必要なら複数使うなり専用品として対策する方向で。
OMRONさんの製品で19インチラックにマウント出来そうな安価な製品ですと「BX50F」でしょうか。
「BX50F」
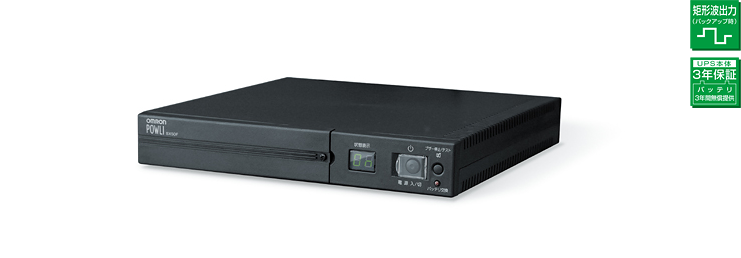
バックアップ容量は500VA/300wなのでもう一息欲しい気もしますが、小型軽量だし、空冷余白や付属パネルを含めても2Uに収まりそうなので実用的かなと。
実は、OMRONさんのBZ50LT2をすでに使っています。一見安っぽいのですが十分に使えています。事故に遭遇したことはありませんが、試験停電させたところ数分保持しました。卓周辺で単体の消費電力が300wを越える製品は多くありませんし、BX50Fは形が違うだけで同等の製品ですから十分使えるでしょう。
#照明器具
2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
年越しは副業の製作です。
小型の製品を組むので暖かいところで作業しています。数年前、プロジェクタを屋外に設置するための箱を作っていたときは寒さとの闘いでしたら天国の様です。
大晦日なのに車で20分の実家にも帰らず何してんだって話ですが、ようやっと心身が回復しつつあるので頑張るしかありません。品物は3種ありますので1日1品やっつけても間に合うのか・・・。
本業に追われる日々が落ち着いたらこの有り様です。シンドイですねぇ。
愚痴っても終わらせるしかありませんので手を進めましょう。
今は基板のハンダ付けが終わったので休憩です。慣れるとリフローハンダは楽です。
この後は基板の配線をチェックし、RaspberryPiと接続して全体の動作チェックと進めます。
除夜の鐘までに今の品物を終わりにすれば少し気が楽になるかな・・・。
そんな作業をしながら Art-Netパッチ のイメージも進めています。
基板の製作は高度になりますが、PaspberryPi-CM4を2-3枚使った構成がいいかなと思ってきました。複数のRaspberryPiをEthernet、I2C、SPIなどで協調動作させるのです。
デスクトップOSが走ってI2CやSPIを扱える条件ですと高価な工業用PCかRaspberryPiしか選択肢にありません。工業用PCは信頼性が高いものの高価で比較的電力も喰います。
アマチュアDIYの延長で考えるならRaspberryPiしかないのかなぁ~って感じです。
キー操作やフェーダーセンシングにはPICを使います。元々そういう用途のマイコンですから、I2CやSPIを使えばRaspberryPiと比較的容易に高速な通信が可能です。
#器具の製作
小型の製品を組むので暖かいところで作業しています。数年前、プロジェクタを屋外に設置するための箱を作っていたときは寒さとの闘いでしたら天国の様です。
大晦日なのに車で20分の実家にも帰らず何してんだって話ですが、ようやっと心身が回復しつつあるので頑張るしかありません。品物は3種ありますので1日1品やっつけても間に合うのか・・・。
本業に追われる日々が落ち着いたらこの有り様です。シンドイですねぇ。
愚痴っても終わらせるしかありませんので手を進めましょう。
今は基板のハンダ付けが終わったので休憩です。慣れるとリフローハンダは楽です。
この後は基板の配線をチェックし、RaspberryPiと接続して全体の動作チェックと進めます。
除夜の鐘までに今の品物を終わりにすれば少し気が楽になるかな・・・。
そんな作業をしながら Art-Netパッチ のイメージも進めています。
基板の製作は高度になりますが、PaspberryPi-CM4を2-3枚使った構成がいいかなと思ってきました。複数のRaspberryPiをEthernet、I2C、SPIなどで協調動作させるのです。
デスクトップOSが走ってI2CやSPIを扱える条件ですと高価な工業用PCかRaspberryPiしか選択肢にありません。工業用PCは信頼性が高いものの高価で比較的電力も喰います。
アマチュアDIYの延長で考えるならRaspberryPiしかないのかなぁ~って感じです。
キー操作やフェーダーセンシングにはPICを使います。元々そういう用途のマイコンですから、I2CやSPIを使えばRaspberryPiと比較的容易に高速な通信が可能です。
#器具の製作
JANDS ESP Ⅱ のレストアを考えていて思ったのですが、Art-NetパッチとJASCIIオフラインを専用ハードウェアで一本化出来ないでしょうか。すでに廃番になった SmartFade にこれらの機能を付与したイメージです。
これまではArt-NetパッチやJASCIIオフラインをPC上で構成して簡易PC卓にもしようと思っていましたが、CmsEditorがPCのOSのアップデートを受けて使えなくなったこともあり、専用ハードウェアで構成した方がいいのかなと思うようになったのです。CmsEditorは10年以上前にWindowsXP_32bitを前提として作っていますので致し方ないのですが、それほど遠くない将来、今回の案件も旧式のパソコンでないと使えなくなるなら専用ハードウェアで作っても同じかなと思うのです。
ただ、専用ハードウェアは維持をするのが楽じゃありません。何時でも手に入ると思っていた重要部品がディスコンになることも珍しくありませんし、アフターケアを考えると部品のストックをしなければなりませんが資金にも保管場所にも限度があります。
どの選択肢をとっても「あちらを立てればこちらが立たず」であり、いずれは維持できなくなると言えばそれまでですが、今のOS事情を見る限りWindowsやMacよりLinuxを母体にした専用ハードウェアの方が長く維持できそうな気がします。
イメージを固める段階ですが、全方位で製作するのは能力的にも時間的にも不可能ですのでどうしたもんかな?って感じです。
#器具の製作
これまではArt-NetパッチやJASCIIオフラインをPC上で構成して簡易PC卓にもしようと思っていましたが、CmsEditorがPCのOSのアップデートを受けて使えなくなったこともあり、専用ハードウェアで構成した方がいいのかなと思うようになったのです。CmsEditorは10年以上前にWindowsXP_32bitを前提として作っていますので致し方ないのですが、それほど遠くない将来、今回の案件も旧式のパソコンでないと使えなくなるなら専用ハードウェアで作っても同じかなと思うのです。
ただ、専用ハードウェアは維持をするのが楽じゃありません。何時でも手に入ると思っていた重要部品がディスコンになることも珍しくありませんし、アフターケアを考えると部品のストックをしなければなりませんが資金にも保管場所にも限度があります。
どの選択肢をとっても「あちらを立てればこちらが立たず」であり、いずれは維持できなくなると言えばそれまでですが、今のOS事情を見る限りWindowsやMacよりLinuxを母体にした専用ハードウェアの方が長く維持できそうな気がします。
イメージを固める段階ですが、全方位で製作するのは能力的にも時間的にも不可能ですのでどうしたもんかな?って感じです。
#器具の製作
大晦日です。
今年も沢山の方々にお世話になりました。
本当にありがとうございます。
新年も皆様にとって良い年になることを祈っております。
お約束のご挨拶をさせて頂きましたが、副業の製作が終わりません。納期が1/8なのでどうしたものか。
製作が終わらないというより、過密業務で疲弊した心身を回復させていたので進められなかったところです。
大晦日の今日になってようやく回復した感じですが、こりゃ正月もノンビリしていられなさそうです。
#器具の製作
今年も沢山の方々にお世話になりました。
本当にありがとうございます。
新年も皆様にとって良い年になることを祈っております。
お約束のご挨拶をさせて頂きましたが、副業の製作が終わりません。納期が1/8なのでどうしたものか。
製作が終わらないというより、過密業務で疲弊した心身を回復させていたので進められなかったところです。
大晦日の今日になってようやく回復した感じですが、こりゃ正月もノンビリしていられなさそうです。
#器具の製作
2023年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する