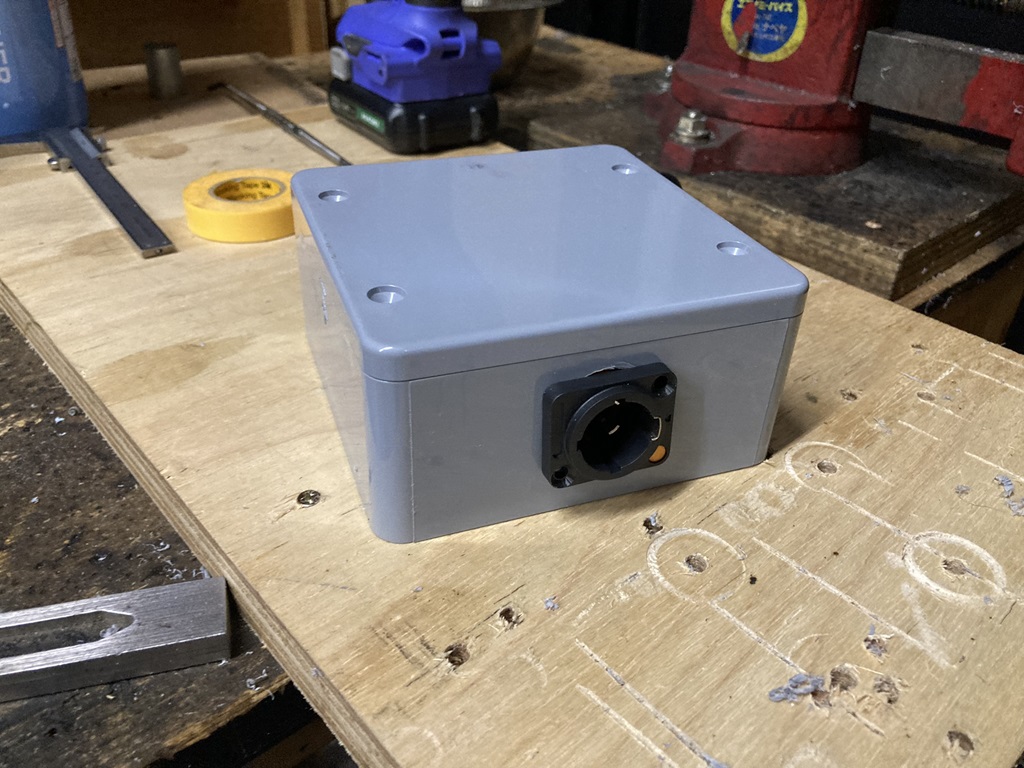全年全月16日の投稿[53件](2ページ目)
2024年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
少し時間が空いたので ArtNet-Patch を考えていました。
部分はなんとなく出来ているので、全体の構造をどうするか。
まずプロセスを分けます。シングルプロセスではたぶんダメ。画面やキーボード操作を親プロセスにし、Art-Net の受信、パッチ処理、送信などを子プロセスとしようかと。子プロセスはタイムアウトする様にし、親プロセスからのリフレッシュが一定時間無ければ自動的に閉じることにします。こうしておけば親プロセスが飛んでも子プロセスがゾンビにならずいいかなと。操作が飛んでも Art-Net は生きている方がいいとする考え方もありますが、タイムアウト処理をコメントにすればそうなります。少なくとも開発中はタイムアウトした方がいいでしょう。
プロセス間は mmap や Pipe で繋ぎます。データには mmap を用い、コマンドには Pipe を用いるイメージです。
子プロセスの Art-Net 処理をイメージしながら表示画面やキーボード操作を考えてみましょう。
#[Art-net] #C言語
部分はなんとなく出来ているので、全体の構造をどうするか。
まずプロセスを分けます。シングルプロセスではたぶんダメ。画面やキーボード操作を親プロセスにし、Art-Net の受信、パッチ処理、送信などを子プロセスとしようかと。子プロセスはタイムアウトする様にし、親プロセスからのリフレッシュが一定時間無ければ自動的に閉じることにします。こうしておけば親プロセスが飛んでも子プロセスがゾンビにならずいいかなと。操作が飛んでも Art-Net は生きている方がいいとする考え方もありますが、タイムアウト処理をコメントにすればそうなります。少なくとも開発中はタイムアウトした方がいいでしょう。
プロセス間は mmap や Pipe で繋ぎます。データには mmap を用い、コマンドには Pipe を用いるイメージです。
子プロセスの Art-Net 処理をイメージしながら表示画面やキーボード操作を考えてみましょう。
#[Art-net] #C言語
2024年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
自宅のメインパソコンのSSDを入れ替える。
プチフリーズを感じることが増え容量不足で不便も感じるので、この際、保守性を考えてAHCIのシングルディスクからRAID1(ミラーリング)にしたい。
今はSSDが安いので手間暇かけるつもりで更新。
当初、OS純正のシステムバックアップを使おうと思ったがWindows7時代の物らしくWindows11では素直に動かない。
EaseUSのDiskCopyを使う。これまではAcronics系を使ってきましたが最近アップデートが弱く、今どきマザーボードでRAID1を扱うことに疑問。EaseUS Disk Copy は Intel-Raidを問題なく扱うらしいのでこちらに乗り換え。
コピー操作の前にレジストリを設定しBIOSをRAIDモードに切り替えRAIDドライバを入れておくは言うまでもありませんが、これらの下準備をして EaseUS Disk Copy を使ったところ難なくコピー出来た。
#パソコン
プチフリーズを感じることが増え容量不足で不便も感じるので、この際、保守性を考えてAHCIのシングルディスクからRAID1(ミラーリング)にしたい。
今はSSDが安いので手間暇かけるつもりで更新。
当初、OS純正のシステムバックアップを使おうと思ったがWindows7時代の物らしくWindows11では素直に動かない。
EaseUSのDiskCopyを使う。これまではAcronics系を使ってきましたが最近アップデートが弱く、今どきマザーボードでRAID1を扱うことに疑問。EaseUS Disk Copy は Intel-Raidを問題なく扱うらしいのでこちらに乗り換え。
コピー操作の前にレジストリを設定しBIOSをRAIDモードに切り替えRAIDドライバを入れておくは言うまでもありませんが、これらの下準備をして EaseUS Disk Copy を使ったところ難なくコピー出来た。
#パソコン
2024年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
道具はどうあるべきか、これは唯一最高を求めればいいと思われがちですがそうではないと考えます。
天才が使う道具と凡人が使う道具は区別するべきだと思うのです。
私は MAdot2 を愛用していますが、言うまでもなく MA2 や MA3 には劣ります。ただ、Fixture が100以下の仕込みならこれほど手早く簡単な明かりを作れるコンソールは無いと思います。複雑なことは出来ませんが、演目に合わせてチカチカ・グルグルしてればいいなら間違いなく生産性が良いのです。もちろん天才的センスとハイレベルなお仕事をお持ちの人は MA2 や MA3 を使うべきですが、「頑張らない明かり作り」をモットーとする凡人の自分には MAdot2 が丁度いい。能力は1/3かもしれませんが価格は1/6。自分がどこまで明かりを作るかどこまで使いきれるかを考えて費用を抑えるのも重要です。MA2 や MA3 は素晴らしいけれど、使いきれない能力にお金を払う意味はありません。
#照明器具
天才が使う道具と凡人が使う道具は区別するべきだと思うのです。
私は MAdot2 を愛用していますが、言うまでもなく MA2 や MA3 には劣ります。ただ、Fixture が100以下の仕込みならこれほど手早く簡単な明かりを作れるコンソールは無いと思います。複雑なことは出来ませんが、演目に合わせてチカチカ・グルグルしてればいいなら間違いなく生産性が良いのです。もちろん天才的センスとハイレベルなお仕事をお持ちの人は MA2 や MA3 を使うべきですが、「頑張らない明かり作り」をモットーとする凡人の自分には MAdot2 が丁度いい。能力は1/3かもしれませんが価格は1/6。自分がどこまで明かりを作るかどこまで使いきれるかを考えて費用を抑えるのも重要です。MA2 や MA3 は素晴らしいけれど、使いきれない能力にお金を払う意味はありません。
#照明器具
2024年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
Windows10以前のパソコンにWindows11 をインストールするには条件があります。適合しないパソコンにはインストール出来ません。
・・・ってのがデフォですが、64bitOSが走るならインストール出来ます。
インストールUSBを作りますと中に「\sources\appraiserres.dll」ってのがあります。以前ならこのファイルを削除することでインストール出来たのですが、今はそれが無理みたい。ですが、Windows10のインストールUSBにある同名のファイルに入れ替えるとインストールが出来るようです。
#パソコン
・・・ってのがデフォですが、64bitOSが走るならインストール出来ます。
インストールUSBを作りますと中に「\sources\appraiserres.dll」ってのがあります。以前ならこのファイルを削除することでインストール出来たのですが、今はそれが無理みたい。ですが、Windows10のインストールUSBにある同名のファイルに入れ替えるとインストールが出来るようです。
#パソコン
2024年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
ホール管理の増員で置きダヌキ。
こういう時はArt-Netパッチの設計を進めるのがいい。いつでも作業を切れるって意味でも不便がありません。
構造においてはマルチプロセス化することがとても重要です。RasperryPi4Bは4コアありますが手続き型処理はもちろんマルチスレッドでも1コア動作が原則。Art-Netの入力、パッチ処理、出力、フロントエンドの処理を同時並行で行いたいのですが、複数のコアで動くかはOS次第とはいえプロセスを分散しておけば1コアだけに負担がかかることは無くなるので良いかなと思うのです。
現在の研究課題はプロセス間通信です。例え一つのアプリケーション内でもプロセスを分けてしまうと同じ変数を触ることが出来ません。これを解消するのがプロセス間通信で、SharedMemory、Pipe、Queueなどの手法があります。それぞれに得手不得手があり、扱いが楽な手法は受け渡しが遅く、受け渡しが速い手法は扱いが難しい傾向があります。このどれを使うかで処理構造が違ってくるので、全体の設計を進める上ではどの手法で繋げるかを予め決めておかないと後が面倒なようです。
注意する点は読み書きのタイミングとデータ枠が可変するかどうかです。勉強中なので説明するのは難しいのですが、この辺りを十分に整理して手段を吟味しているところです。
#C言語 #[Art-Net]
こういう時はArt-Netパッチの設計を進めるのがいい。いつでも作業を切れるって意味でも不便がありません。
構造においてはマルチプロセス化することがとても重要です。RasperryPi4Bは4コアありますが手続き型処理はもちろんマルチスレッドでも1コア動作が原則。Art-Netの入力、パッチ処理、出力、フロントエンドの処理を同時並行で行いたいのですが、複数のコアで動くかはOS次第とはいえプロセスを分散しておけば1コアだけに負担がかかることは無くなるので良いかなと思うのです。
現在の研究課題はプロセス間通信です。例え一つのアプリケーション内でもプロセスを分けてしまうと同じ変数を触ることが出来ません。これを解消するのがプロセス間通信で、SharedMemory、Pipe、Queueなどの手法があります。それぞれに得手不得手があり、扱いが楽な手法は受け渡しが遅く、受け渡しが速い手法は扱いが難しい傾向があります。このどれを使うかで処理構造が違ってくるので、全体の設計を進める上ではどの手法で繋げるかを予め決めておかないと後が面倒なようです。
注意する点は読み書きのタイミングとデータ枠が可変するかどうかです。勉強中なので説明するのは難しいのですが、この辺りを十分に整理して手段を吟味しているところです。
#C言語 #[Art-Net]
2024年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
寝床というか2x4材の接合部で使う丸ナットが完成しました。
3Dプリンタで肉厚にプリントしたD断面の丸棒の横っ腹にステンレスのM8インサートを入れています。インサートナットの外ネジは細ピッチM10ですのでタップを切って捻じ込んでエポキシ接着剤で固定しています。

本業の合間に穴空け治具も進めています。
この方式で十分な強度が出れば2x4材の用途が広がる気がします。
#ガチ工作
3Dプリンタで肉厚にプリントしたD断面の丸棒の横っ腹にステンレスのM8インサートを入れています。インサートナットの外ネジは細ピッチM10ですのでタップを切って捻じ込んでエポキシ接着剤で固定しています。

本業の合間に穴空け治具も進めています。
この方式で十分な強度が出れば2x4材の用途が広がる気がします。
#ガチ工作
PegasysG10 のリペアを進めていますが現場や他の製作物もあるので牛歩状態です。10台終わりましたが、全48台なのでまだまだです。
それにしても飽きてきました。手順がまとまったので新鮮味がありません。モノ造りは好きですが、生産ではなく開発が好きなんですよね。
そんな心持ちで進めているところ、筐体の貼り合わせ部の防水がゴムパッキンではなくコーキングガチガチのに遭遇。1日に2台しか出来ないのがコレでして、マイナスドライバを加工した専用のノミとワイヤブラシでひたすら落としていきますが、コーキングを取り去るのにとても時間がかかるので心が折れます。
#器具の修理
それにしても飽きてきました。手順がまとまったので新鮮味がありません。モノ造りは好きですが、生産ではなく開発が好きなんですよね。
そんな心持ちで進めているところ、筐体の貼り合わせ部の防水がゴムパッキンではなくコーキングガチガチのに遭遇。1日に2台しか出来ないのがコレでして、マイナスドライバを加工した専用のノミとワイヤブラシでひたすら落としていきますが、コーキングを取り去るのにとても時間がかかるので心が折れます。
#器具の修理
2024年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
本業はオフで自宅の工作部屋の片付けです。足の踏み場がギリギリの部屋です。
出て来る出て来る行方不明だった部品たち、こんなに買ったのかと呆れる部品たち(^へ^;
発掘された部品を出来るだけ丁寧に分類・再梱包して収納します。
あとは、今後参考にすることは無いであろうWindowsXP時代のプログラミングマニュアルたち。
今となってはWindowsAPIを直に触ることはありませんし、VisualBasicなど書くことはありません。そんな本が20冊以上ありますのでこれも処分です。
#雑記
出て来る出て来る行方不明だった部品たち、こんなに買ったのかと呆れる部品たち(^へ^;
発掘された部品を出来るだけ丁寧に分類・再梱包して収納します。
あとは、今後参考にすることは無いであろうWindowsXP時代のプログラミングマニュアルたち。
今となってはWindowsAPIを直に触ることはありませんし、VisualBasicなど書くことはありません。そんな本が20冊以上ありますのでこれも処分です。
#雑記
2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
JANDS ESPⅡ 24ch が手元にあります。
シンプルで芸はありませんが、ちょっとした現場には便利な調光卓です。ただ齢30歳ともなりますと物理的に寿命です。フェーダーのスライドボリュームにガリが出てるのはもちろんですが、プリント基板の銅箔が腐食して断線しているところもあります。
不調のためここ数年使っていませんでしたが、苦楽を共にしてきた相棒ですので捨てるのは忍びなく修理というかリビルドしてあげようかなと思い始めました。
メイン基板には痛みはありませんので、主にフェーダー基板の再生です。使われている日本抵抗器製のスライドボリュームは随分前に廃番になっていますし、基板もやられているので、入手可能なスライドボリュームを使ったフェーダー基板を丸々新造するのが現実的な対策です。
問題は費用です。pcbgogoさんで見積もったら400x400mm(仮のサイズ)の両面基板が1枚52USDくらい。スライドボリュームは千石電商さんで580円くらいだけど、中華電機なら60円くらい。手間はともかく案外安く済みそう。
最近は一般照明卓の選択肢が少なくなり、手に入っても機械的に廉価な物ばかりなので、JANDS ESPⅡ が10万以下で復活するならアリですね。
#器具の修理
シンプルで芸はありませんが、ちょっとした現場には便利な調光卓です。ただ齢30歳ともなりますと物理的に寿命です。フェーダーのスライドボリュームにガリが出てるのはもちろんですが、プリント基板の銅箔が腐食して断線しているところもあります。
不調のためここ数年使っていませんでしたが、苦楽を共にしてきた相棒ですので捨てるのは忍びなく修理というかリビルドしてあげようかなと思い始めました。
メイン基板には痛みはありませんので、主にフェーダー基板の再生です。使われている日本抵抗器製のスライドボリュームは随分前に廃番になっていますし、基板もやられているので、入手可能なスライドボリュームを使ったフェーダー基板を丸々新造するのが現実的な対策です。
問題は費用です。pcbgogoさんで見積もったら400x400mm(仮のサイズ)の両面基板が1枚52USDくらい。スライドボリュームは千石電商さんで580円くらいだけど、中華電機なら60円くらい。手間はともかく案外安く済みそう。
最近は一般照明卓の選択肢が少なくなり、手に入っても機械的に廉価な物ばかりなので、JANDS ESPⅡ が10万以下で復活するならアリですね。
#器具の修理
2023年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する