塗装前まで終わったのですが、ほんの少し寸法を間違えました。肝心の番重が入るようで入りません。
木ボンドが硬化しないと修正作業は出来ませんので、修正治具を作って本日は閉店。
明日は大晦日ですが、修正して塗装を2層塗りまで終わりにしたいですね。
例年の通り正月大掃除を実施します。それまでに使える状態になるかなぁ~。
#ガチ工作
2021年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する




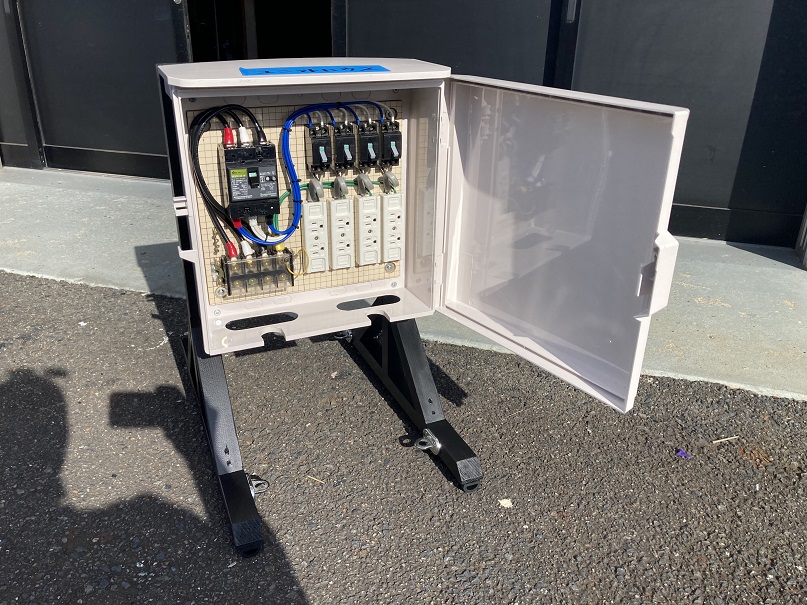

2021年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する






2021年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する